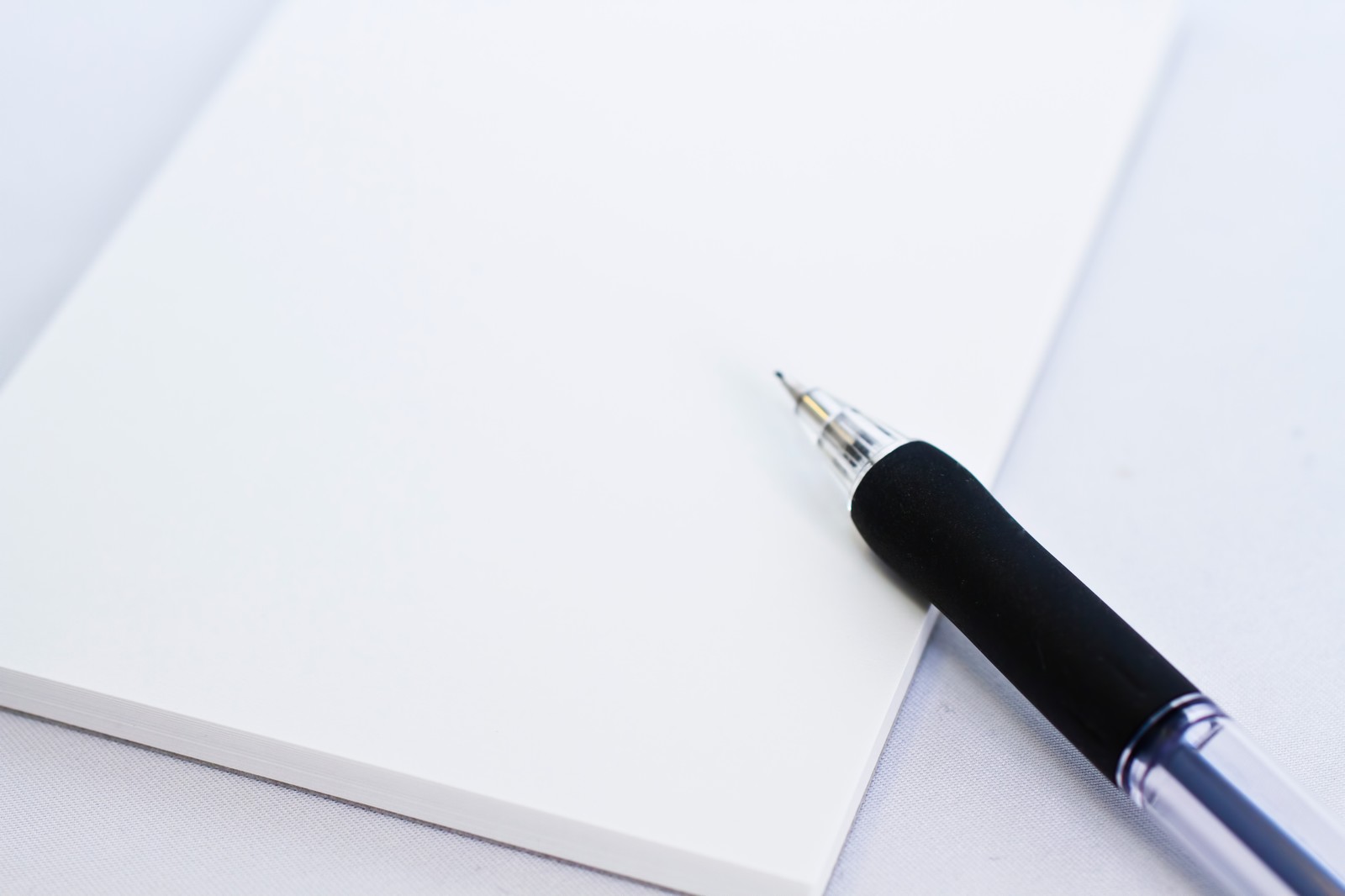先日「書き言葉」と「話し言葉」について、このブログの記事を更新した。
記事の最後は「あなたは『読んで』いますか?それとも『聴いて』いますか?」と締めくくったところ、Facebook上でいくつかコメントをいただいた。
実はその記事を書く時、僕はちょっとした「実験」を行っていた。
いただいたコメントからその実験についての回答と、僕の中で新しい考えが得られたので改めて書こうと思う。
記事についてのコメント結果
そもそもブログの読者数自体が少ないので、コメントをいただいた数はそれほど多くはなかった。
しかし、僕があらかじめ欲しかった回答者のタイプが出揃ったのは幸運だったと思う。
僕が欲しかった回答者のタイプとは、「男性と女性の両方」と「リアルで僕に会ったことのある人と、会ったことのない人」。
前者はいわゆる「左脳タイプ」と「右脳タイプ」と同じで、男性と女性で回答に違いがあるのか知りたかったから。
後者は僕の声や外見を知っているかどうかで、回答に違いがあるのかを知りたかったから。
そしてコメントをいただいた方たちの回答は、全員「聴いている」だった。
これらの回答を得て、僕はあえて言い切る。
僕が先日の記事で書いた文章を、男性も女性も、実際に会ったことのある人もない人も、「読んでいる」ではなくて「聴いている」のだ。
この結果は、正直なところちょっと意外だった。
なぜなら僕はその記事を、意図的に「話し言葉」から「書き言葉」に寄せて書いたからだ。
なぜ、そんな「実験」をしたか?
理由はひとつだけ。
ブログを書く際に、「文章をどのくらい『書き言葉』に寄せて書いても、読者に『聴いてもらえる』かどうかを知りたかったから」だ。
そしてその答えは、実際に文章を書いて読者の反応がないとわからない。
「このくらいなら『書き言葉』によせても大丈夫」という感覚は、実際に試してみないとわからないのだ。
だからコメントをいただいた読者の方々には、心から感謝している。
「実験」をしてまで読者の反応が知りたかった理由
僕はこのブログの記事を、基本的には「読む」のではなく、「聴いて」欲しいと思っている。
「読む」よりも「聴いて」もらった方が、僕の伝えたいことが伝わりやすいと考えているからだ。
なので、「どのくらい『書き言葉』に寄せて文章を書いても、読者に『話し言葉』として感じてもらえるかどうか」
その境界線を知ることは、僕にとってとても重要なことなのだ。
では、全て「話し言葉」で書けばいいのか?
全て「話し言葉」に振り切って書く。「完全な話し言葉」だ。
読者に「聴いて」欲しいのなら、そうするべきだと思うかもしれない。
しかし、それは2つの理由から得策ではないと僕は考える。
1つ目は、「完全な『話し言葉』は、ブログ上で意味が通らない」こと。
2つ目は、「僕が『話し言葉』に寄せた文章が書けないテーマがある」こと。
次はこれら2つの理由について、説明する。
「完全な話し言葉」は意味が通らない
そう。「完全な話し言葉」はブログにおいて意味が通らないのだ。
極端な話、誰かに僕の話を「完全に聴いてもらいたい」なら、その方に会って直接話をすればいい。
ただ、当然そんなことは無理だ。
そこで僕は、ブログを伝える手段として使用している。
そしてブログには「文章を書いている」。
当たり前だと思うだろうか?
しかし「文章を書いている」以上、「完全な話し言葉」を使って人にものを伝えることは不可能なのだ。
この「書き言葉」と「話し言葉」の違いを説明するのに、わかりやすい例として夫婦の会話を「書き言葉」と「話し言葉」で書いてみる。
まずは「書き言葉」。
妻「ねえ、今日帰ってくるの何時?」
夫「だいたい7時くらいかな。」
妻「7時ね。わかった。」
同じ内容を伝えるのに、今度は「話し言葉」。
妻「ねえ、」
夫「・・・あ、7時?」
妻「ん。」
いかがだろうか?
あなたは、いきなりこの文章を読んで、「書き言葉」と同じ内容を理解できただろうか?
おそらく難しいと思う。
本当は「話し言葉」にも「ナチュラリズム(自然主義)」と「リアリズム(現実主義)」があって、この例は「リアリズム」で書いた。
ちなみに、芝居やドラマの脚本に多用される「ナチュラリズム」で書くとこんな感じ。
妻「ねえ、何時?」
夫「ん?」
妻「帰り。」
夫「あぁ、・・・7時くらい?」
妻「わかった。」
ここに「演技」という技術や「見せ方」という演出が入ることで、初めて「話し言葉(ナチュラリズム)」は第三者にその内容を伝えることができる。
そして脚本家の立場から言うと、実は第三者は観客や視聴者ではない。
脚本家の次に原稿をみる人たち。つまり「役者」や「演出家」に内容を伝えるためにギリギリのラインで言葉をつづっているのだ。
少し脱線したので、話を戻す。
ブログという「『文章』を使って人にものを伝える」手段を選んでいる以上、「完全な話し言葉」でその内容を伝えることはできない。
このことがわかってもらえたのではないかと思う。
「話し言葉」に寄せられないテーマがある
次に「完全な話し言葉」をこのブログに使えない、2つ目の理由について。
僕がこのブログを使って伝えたいテーマの一つに、「メンタルに苦しんでいる人にむけての文章」がある。
その際、自分の経験談を使って思いを伝えることがある。
自分の経験だけは、僕が間違いなく理解したものだからだ。
ただメンタル関係の経験談は、僕自身がある程度客観性をもっていないと書くことができない。
経験談だからできるだけ主観的にしようと努めているが、現時点では客観的な立場にいないと文章を書くこと自体ができないからだ。
その結果、主観性だけの「完全な話し言葉」ではなく、多少の客観性を持った「『話し言葉』に寄せた言葉」をこのブログには使うこととなる。
僕が今回の「実験」を行った一番の理由はこれだ。
僕が伝えたいことがある時、「どの程度『書き言葉』によせた『話し言葉』で文章を書いても、人に『聴いてもらえる』ことができるか?」
「実験」を行った意味は、僕にとってとても大切なものなのだ。
「書き言葉」と「話し言葉」 記事にしてみえてきたもの
僕はこのブログを書くことによって、誰かに何かを伝えたい。
その「伝える」という力において、「書き言葉」と「話し言葉」のバランスはとても重要なのだ。
今回の「書き言葉」と「話し言葉」の記事を書いて、僕が今まで認識していたそのバランスを修正することができた。
新しく手に入れたそのバランス感覚を大切にして、僕はこれからも何かを人に伝え続けたい。
cotaka
最新記事 by cotaka (全て見る)
- 人間関係を良くするとは? - 2018年4月25日
- 【無料体験セッションのご案内】 - 2018年4月20日
- 「なんでわからないんだ!」について - 2018年4月20日
スポンサーリンク