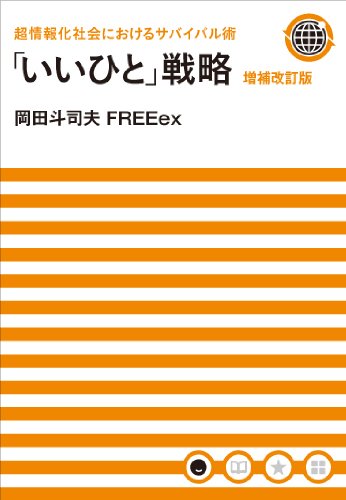こんばんは。cotakaです。
最近、職場で若い人たち(完全におじさんの言い方ですが、職場には10~20歳以上離れたひとがたくさんいるのです)のと話していると、どうやら僕が思う「いいひと」と彼らの使う「いいひと」の定義が違うような気がすることがあります。
うまく言えないのですが、「いいひと」との距離感が今の若い人たちは遠いような感じがするのです。僕が思う「いいひと」は極端な話、直接会ってみないと本当に「いいひと」かどうかわからないと思うのですが、彼らのいう「いいひと」にはもっとライトな印象を受けることが多いのです。
この感覚の違いはなんだろう?どこから来るんだろう?と思っていた最中、ちょうど参考になりそうな本、「『いいひと』戦略 岡田斗司夫」を見つけたので、一体この「いいひと」というものに感じる違和感がなんなのか、探ってみようと思いました。
岡田さんは、ネット世代の若者は「今、ここ」にいる自分の気持ちを大事にすること、いわば「自分の気持ち第一主義」になっていて、他人を判断する基準はその人の能力などよりも、自分が「その人を見てどう思ったか?」「見た目」「印象」の方が尊重されるようになっていると言います。
そしてそのひとの「印象」にはSNSなどネット上における「印象」も大きく影響していると。
言い換えるならば、今までは貨幣と商品を交換していた「貨幣経済社会」だったのに対し、評価と影響を交換する「評価経済社会」に現代は突入している。
つまり、仕事のできるイヤな人100人と仕事をするよりも、1000人の普通の「いいひと」と仕事をすることを好むようになっているそうです。
ただし、いくら普通の人とはいえ、「いいひと」を1000人集めたコミュニティーを作るためには、自分を「いいひと」のひとりとして、きちんと「キャラクター上場」をしておかなければなりません。
「いいひと」であることが多くの人に知れ渡っていなければ、決して「いいひと」はその周りに集まってくれないからです。
「いいひと」でないと知れ渡ることは、現代の「評価経済社会」では生き残っていけないのです。
この後、本の中盤から後半にかけて、「いいひと」であることで損をするように見えるという意見に対する反論や、どのように自分を「いいひと」として世間に認知させるかについて、段階を踏まえながら実に見事に「戦略」を解説していきます。
そうです。この本は「いいひと」になるための『方法』を説いた本ではなく、あくまで『戦略』を説いた本なのです。
この本を読んで、僕が若い世代に感じていた「いいひと」に対する感覚の違和感が少しわかった気がします。
若い世代の人たちは、生まれた時から、もしくは物心がついた頃にはもうネットが当たり前にあった、まさに「ネイティブ」なネット世代です。
大学生になるくらいまで、手元に携帯電話もなかった僕たちとは現実とネットの世界の境界線の感覚が根本的に違う、「ネイティブ」は自分が「ネイティブ」であることさえ気づきませんから、感覚が違って当たり前なのです。
それじゃあ、僕はどうするか?このままついていけないとあきらめるのか?
そんなわけありません。「ネイティブ」でないことがわかったのなら、自分で勉強して「ネイティブ」の方法を学ぶだけです。
それは若い世代に迎合するという意味ではありません。
これから若い世代が作り出していく社会の根本に「ネイティブなネット世代であること」があることに気づいたのなら、その武器を手に入れてさえしまえば、彼らが決して手に入れられない「経験」をそこに足した「最強のおじさん」として、社会の中心にいられることも十分可能となるのです。
よっしゃ、面白そうだ。「最強のおじさん」になってやろうじゃないの。
cotaka
最新記事 by cotaka (全て見る)
- 人間関係を良くするとは? - 2018年4月25日
- 【無料体験セッションのご案内】 - 2018年4月20日
- 「なんでわからないんだ!」について - 2018年4月20日
スポンサーリンク